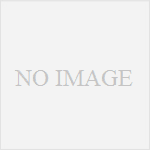大会シンポジウムについて思うこと
寒暖の差が大きく、体調維持に苦労する日々が続いています。皆さま、お変わりなくお過ごしでしょうか。
去る12月3日(日)、今年度の大会・総会が日本大学経済学部のキャンパスで開催されました。午後の大会シンポジウムは、「近現代の人間社会と自然をめぐるふるまい」というテーマで、空由佳子氏(フェリス女学院大学)による論点開示に続いて、きわめて興味深く充実した報告とコメントがなされました(公式ウエッブサイト参照)。報告とコメントをされた水野祥子(駒澤大学)、太田淳(慶應義塾大学)、小仁田章(昭和女子大学)、伊藤毅(青山学院大学)の各氏、およびシンポジウムに参加してくださった皆さんに、心から御礼申し上げます。
三報告を聞いてとりわけ印象深かったのは、「近代」を論じる枠組みや形式が、戦前の「日本資本主義論争」から「戦後歴史学」にかけての時期のそれとは明白に異なっていたということでした。
「日本資本主義論争」は、明治維新の性格や革命戦略などをめぐって「講座派」と「労農派」のあいだで闘わされた論争でした。一方の「講座派」が明治維新は「絶対主義的改革」であり、したがって当面目指すべき革命は「ブルジョア民主主義革命」だとしたのに対して、他方の「労農派」は、明治維新はまがりなりにも「ブルジョア革命」であり、当面の革命は「社会主義革命」だと主張しました。両派の見解の対立はたいへん激しいものでした。にもかかわらず、両派のあいだには奇妙な一致が見られました。両派とも、マルクス主義的な発展段階論を前提として明治維新とそれ以後の日本社会を理解しようとする志向を強くもち、「日本の近代は近代ではない」「日本の近代は歪んだ近代である」という言説の形式をとっていたからです。このような言説の形式が成立したのは、もちろん、述語における「近代」が「西欧近代」を意味していたからでした。この言説形式は「戦後歴史学」にも継承され、1960年代まで存続したように思います。
本年度のシンポジウムでの三報告は、「日本資本主義論争」から「戦後歴史学」までを支配していたこのような言説形式とはまったく無縁であると感じさせるものでした。三報告がいずれも、植民地下や半植民地下にあったアジアやアフリカの「近代」を対象としたものであったこともそのことと関連していたのかもしれません。それぞれの地域の「近代」は、西欧の衝撃とその対応という次元にとどまることなく、その地域の人びとの主体的な営みをも含むさまざまな要素の複合体としてその具体的あり方が問われていました。ですから「近代」とは、地域の違いや時間の経過のなかで語りなおされ、新たな考察の対象となる性格をもつ基本概念であると考えるべきものなのかもしれません。そもそも「近代」は、明治維新以来ずっと問題とされてきたのですから、今から100年後も相変わらず語られ、考察され続けられているのではないか、そういうことを強く感じさせられたシンポジウム報告でした。
2023年12月 歴史学会会長 松浦義弘