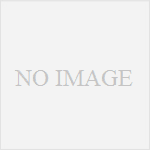マイノリティ史研究における主体性と構造
近年、日本社会におけるマイノリテイへの不寛容が、様々な局面で問題化している。在日韓国・朝鮮人を対象としたヘイトスピーチ、アイヌに対する排斥的な言説、移民に対するゼノフォビア的反応、
LGBTに対する人権侵害、妊娠に関する女性への差別的発言 。さらに、国会議員や地方議員、著名な作家など社会的影響力のある人物によって、排斥や差別がさまざまなかたちで称揚されているということが、問題にいっそう深刻な色を加えている。
例えば「労働移民」受け人れの必要性を指摘した作家は、一方でアパルトヘイト廃止後の南アフリカの住宅状況を否定的に論じて「居住だけは別にした方がいい」と記した。このコラムは内外の批判を浴びたが、それでもなお「リトル東京」や「チャイナ・タウン」を引き合いに出し、強制的隔離政策を支持していない、自発的な居住地の棲み分けは称揚されるべきだと反論した。しかし、「自発」とは、果たしてどのような状態なのであろうか。「強制」の対概念と単純に措定してよいのであろうか。ここに、日寸事問題を超えた歴史的な問いが存在している。
というのも、社会におけるマイノリティ集団を対象とした歴史研究は、長らく「強制」と「自発」を大きな枠組みにしてきた。すなわち、征服・植民地化・支配の構造を解き明かすことによって従属的存在とされる「客体としてのマイノリティ」という視座か、あるいは支配構造に対して抵抗する「主体としてのマイノリティ」という枠組である。
しかしながら、近年の歴史学は、構造と主体の関係について、いずれかに歴史の起動力を還兀せず、より複雑な権力作用のあり方を解明するものとなっている。主体は構造に影響されながら形成されるが、その制約の中で主体は選択・行為し、構造そのものに影響を及ぼし返していく。マイノリティ史研究においても、単純な強制と抵抗の二分法を超え、両者の関係の中に権力の作用を見ることによる新たな地平が切り開かれつつある。
そこで、今年度の歴史学会大会シンポジウムでは、時代・地域の異なるマイノリティ集団を取り上げる。歴史の中でそれらが、社会全体の構造との関係にいかなる影響や制約を受けながら、構造に対して働きかけてきたのか、その結果としていかなる状況が形成されてきたのかを考える。さらにそれらの比較検討を通じて、主体性と構造の関係史における成果や課題を共有したい。
以上の問題意識から、今回は3名の方々に報告をお願いした。
檜皮瑞樹報告では、19世紀のアイヌの訴願・逃亡といった行動や、強制移住への対応を取り上げ、和人との関係のなかでのアイヌの主体的営為を読み込み、客体化されたアイヌ像を改めて問い直す。
南川文里報告では、第二次世界大戦を挟んだ在米日系人社会というエスニック・コミュニティの解体と再編、そして「日系アメリカ人というイメージの編制が、どのようなメカニクスによってなされたかを探る。
大川謙作報告では、20世紀チベットの位置づけをめぐるポリティクスについて、中国とインドとの関係を軸に、「排除」と「包摂」というキーワードを手掛かりに考察する。
歴史学会では、2012年度大会「戦後歴史学とわれわれ」、2013年度「歴史学における図像史料の可能性一版画・広告・ポスター」、そして2014年度「軍隊と社会・民衆」というテーマで近年シンポジウムを積み重ねてきた。戦後歴史学の再検討を経たうえで、「図像史料」「軍事史」そして今回の「主体性・構造」というテーマを設定してきたわけだが、これらは以前から歴史学のなかで議論されてきたテーマであるともいえる。しかし、そのような従前のテーマを見つめ直し、その新たな動向を踏まえつつ、様々な問いを喚起することによって、対象とする時代や分野を横断した問題意識を共有する方策としてきたのである。今回もそのような歴史学会の近年の流れに沿う企画である。多くの方々が参加され、活発な議論となることを期待したい。
歴史学会企画担当